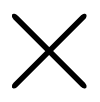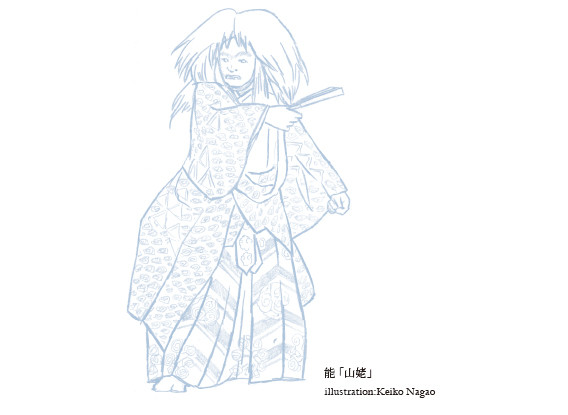News & Contents
- 2025-11(3)
- 2025-09(2)
- 2025-08(1)
- 2025-04(1)
- 2025-03(2)
- 2024-11(1)
- 2024-10(2)
- 2024-08(3)
- 2024-06(2)
- 2024-04(1)
- 2024-03(2)
- 2024-02(1)
- 2024-01(3)
- 2023-12(1)
- 2023-10(4)
- 2023-09(3)
- 2023-08(2)
- 2023-07(1)
- 2023-06(2)
- 2023-05(2)
- 2023-04(3)
- 2023-01(1)
- 2022-12(2)
- 2022-10(2)
- 2022-09(4)
- 2022-06(1)
- 2022-05(4)
- 2022-04(1)
- 2022-01(3)
- 2021-12(1)
- 2021-11(2)
- 2021-10(3)
- 2021-07(2)
- 2021-06(1)
- 2021-05(4)
- 2021-01(1)
- 2020-12(1)
- 2020-11(2)
- 2020-09(2)
- 2020-05(1)
- 2020-03(1)
- 2020-02(1)
- 2019-12(3)
- 2019-11(7)
- 2019-09(1)
- 2019-06(2)
- 2019-05(1)
- 2019-04(3)
- 2019-03(4)
- 2019-02(5)
- 2019-01(1)
- 2018-11(4)
- 2018-09(6)
- 2018-08(5)
- 2018-05(2)
- 2018-04(2)
- 2018-02(5)
- 2018-01(2)
- 2017-12(3)
- 2017-11(1)
- 2017-09(5)
- 2017-08(2)
- 2017-07(4)
- 2017-06(2)
- 2017-05(4)
- 2017-03(1)
- 2017-01(4)
- 2016-12(3)
- 2016-10(1)
- 2016-09(1)
- 2016-08(3)
- 2016-07(6)
- 2016-06(4)
- 2016-05(1)
- 2016-04(1)
- 2016-01(1)
- 2015-12(3)
- 2015-11(3)
- 2015-10(1)
2021/07/10
「荒い息、詰まる息」 文・長尾契子(『1/f』vol.9 掲載記事)

背骨担当者の一声。
今日も西武新宿線に乗る。 車内の適当なスペースに身を滑り込ませると、ハンドバックの中をまさぐって携帯を取りだし、俯いてディスプレイ上に人差し指を滑らせる。「今のうちに返信を」と思う前に身体が動いた、その次の瞬間にはっとする。私の中に棲む〝とある担当者〟から「背骨のムダ遣い」といつもの囁きが聞こえたからだ。
中学生の頃、習いごとのやり過ぎで腰椎にくっついている椎弓(ついきゅう)を疲労骨折し、長いコルセット時代を送った上、デザインを始めてからはストレートネックによる医者通いと、背骨と向き合う日々を送ってきたからだろうか。不必要に姿勢をこごめることを「背骨のムダ使い」と呼ぶようになった。
ダンゴムシのように背を丸め集中しなくてはならないことは山ほどある。外出時くらいは身体を伸ばしておかないと、後で冷凍シーフードミックスのパックみたいにガチガチになっている。「ムダ遣いしたからだよ」と〝背骨担当者〟はつれない。こごめてはハッと伸ばし、丸めてはアッとねじる。そんな気遣いもむなしく呼吸は浅いままだった。
「現代人は姿勢が悪い」、とだれかさんが呟いた。聞き慣れた言葉が耳の奥でこだまし、いくつもの声となって混じり合ったのちに消え、やがてのっぺらぼうになった。
一方で、都会の背骨ムダ遣い生活から離れてゆったりと呼吸がしたくなり、自然豊かな地方の旅先や、坐禅をするために訪れた古都で「現代人は姿勢が…、息が…」といつものフレーズを耳にすると、早々に坐布(ざふ)から腰をずらしたくなる。都市のすみっこで生かされてきた者として言い返したくなる。耳に突っ込んだイヤホンも、視界を狭めるためにかけたサングラスも、目深に被った帽子も、俯き加減の姿勢も何もかも、街に飽和している情報やノイズから身を守るためのプロテクターではなかったか。
私には密かに〝尊敬する背骨〟を持つ人がいる。専門学校時代、都内某所にある老舗のとんかつ屋で見た、その店の主人である彼の背は、長年の仕事柄か、前傾したいかり肩から伸びる首が前方に向かってほぼ直角に曲がっていた。カウンターの中ですっくと直立している姿を一度も見たことがない。はぜる油の中で、徐々にきつね色に彩られていく無数のとんかつを見つめ続けてきた職人の背には、息を呑むような気魄があった。〝姿勢が悪い〟という言い方を無効にしてしまう背骨だった。千切りキャベツの缶にしわしわの手を器用に突っ込む姿を見ながら、淡々とした深い呼吸が手際の良い作業と呼応し合っていることに気づいた。
姿勢そのものに良し悪しが言えないように、息が上がったり詰まったりすることにも良し悪しはないのではないかと気づいたのはこの時だった。丁寧で深い呼吸がもたらす効用は、先人たちによってすでに実証され、極められてきた。今日は少し視点を変えて、ふだんは陽の当たらない、詰まる息、荒ぶる呼吸を東京のすみっこで取り上げてみたい。
『人生の哲学』渡邊二郎[著](角川ソフィア文庫)渡邊が放送大学の教員時代に作成した印刷教材の中で、1998年に発刊したものが文庫版として2020年に再版された。
詰まる息ーー「愛」の語源。
息が詰まるのはどんな時だろう。初対面での打ち合わせや、苦手な人にどうしても会わなければならない時、不安や恐れに囚われている時などだ。一方で、好きなことをしている時や、愛する人と一緒に過ごす時間にも呼吸が早まり、息が上がったりする。愛する人と一緒に居るのは、安心と喜びに包まれた幸せな時間のはずなのに、苦しくなることさえある。呼吸の乱れという身体の現象が、心の状態によって引き起こされることは、心身が分かち難く結び合っていることを示している。息は心と身体をつなぐ窓口の役目を果たし、心の複雑を映す。この不可解なあべこべ状態が、「愛」という漢字の語源の中に、すでに刻み込まれていることを知った。
実存思想、現象学、ドイツ古典哲学など、多岐にわたる哲学分野の研究者として知られる渡邊二郎(1931~2008)の『人生の哲学』(角川ソフィア文庫、2020年)から引用してみる。
渡邊は、誰もが直面する「生」の問いを「死と生を考える」、「愛の深さ」、「自己と他者」、「幸福論の射程」、「生きがいへの問い」という5つに絞り、古今東西の哲学・文学・詩歌などを多彩に引用しながら平易な言葉で解明していく。「愛の深さ」の章では、「愛」という概念そのものを、漢訳仏典に見られる漢字の語源に着目し、解像度を高めながら検証している。
愛という字は、もとは、「旣」(き)と「心」とを合わせてできた字であるとされている。「旣」は「皀(ひゅう)」(食物)が喉に閊(つか)えて咽(むせ)び、息が詰まることを表した字である。したがって、それと「心」とを合わせた「愛」という字は、「心が強く打たれて息が詰まるような思いになること」を表していたとされている。
ではどうして、息が詰まるのだろうか。
それは、「歎」(たん)と同様に、心が強く動かされて、嘆くありさまを示していたわけである。転じて、「愛」は「慈しむ」という意味にも使われたという。この「旣」と「心」とを合わせた字を簡略化して、さらに「旡」(き)と「心」とを合わせた文字「㤅(あい)」が作られたという。この字は、「元気のない意」を表したとされる。この字の下に、「静かに行く意」を表すところの「夂(ち)」という字を加えてできた文字の変形が、今日の「愛」という字であると言われている。したがって、「愛」は、「元気のない足どりで行くこと」も表すとされる。
愛とは「心が強く打たれて息が詰まるような思い」になり、「元気のない足どりで静かに行く」ことに他ならない。人が思い悩む代表的なシーンがコラージュのように一文字の中に刻み込まれている。「愛の思いが深くなった時、人は、胸が閊(つか)えて、息苦しくなり、あまりにも重い心を抱いて、元気がなくなり、蹌踉(ふらふら)として、足を引き摺り、行き悩んでしまう」と記している。
愛についてイメージされがちな、朗らかで若々しい姿はここにはない。「心の奥底に、分裂や葛藤が潜み、人間の魂が、一筋縄ではゆかない多様な要素」を含み、「自己のうちの二元的な対立や矛盾が自覚される」から苦しい。渡邊にとって「愛を知る人」とは、「愛を考え、深く悩む人」であった。
「愛」という一字は実に複雑な遍歴を持つ語であり、中国で、日本で、その成り立ちは諸説ある。明治以降、外来語が入ってきた際もさまざまな解釈と使われ方をしたし、現在もその変化は続いている。その中の一つ、漢訳仏典に記された中に、「食べものが喉につかえて咽び息が詰まる」身体の様相にたとえて愛に関して人の心のありさまを映し出そうと苦慮した、いにしえの人々がいたのだと思うと、はるかな気持ちになる。
荒ぶる息ーー能「山姥」より。
2020年の夏に禅僧の藤田一照さんと能楽師の安田登さんによる対話講座が新宿で開かれた。会のテーマは「〈たましひ〉という深淵に触れる」。「〈たましひ〉をどこかに置き忘れたような生き方を強いられているような現代において、われわれの先人たちが〈たましひ〉という言葉に込めたリアルな情緒を、あらためて味わい直す努力が必要ではないか」(パンフレットより)。そんな問いから組まれた講座は、古代文字、日本の古典、西洋文学、能、禅など、あらゆる知見を互いに持ち寄って掘り下げながら、時にユーモアで室内をどっと沸き立たせつつ、〈たましひ〉とは何かを2時間ノンストップで対話しづつける内容。2019年の秋に開かれた第一回に参加した私にとっては(『エフブンノイチ 8号』のあとがきを参照)前回の続編となったが、どちらも「〈たましひ〉の語源」が導入となった。〈たましひ〉は英語では spirit(スピリット)。ラテン語のspirare(スピラーレ)が語源で、元々〈息〉を表している。
こうして〈息〉を足がかりとして進む中、安田さんは禅の仏教学者、鈴木大拙がおこなっていた能研究の一部から『山姥』という演目を紹介される。大拙はこの能に登場する山姥の姿に、日本で非言語的なかたちで伏流してきた「愛の原理」が投影されていると考えた。
まず、山姥伝説を曲舞に仕立てて演じ評判を得た都の遊女、百魔山姥(ひゃくまやまんば)(ツレ)が登場する。彼女は供の者(ワキ・ワキツレ)を連れて善光寺詣に出かけた。上路越(あげろごえ)の難所に差し掛かったところで、にわかに日が暗くなってしまう。そこに一人の女(前シテ)が現れる。女は「自分こそが本物の山姥である」と明かして、遊女に「供養として曲舞を奏して、私の迷妄を晴らしてほしい」と告げた後、どこかに消えてしまう(中入)。辺りは元のように明るく戻った。所の者(間狂言)が山姥の正体についての俗説を語るが、その荒唐無稽ぶりに供の者から一笑に付される。
夜になった。月光澄み渡る中、遊女が曲舞を舞っているところに、あの山姥(後シテ)が真実の姿で登場する。髪は雪を戴いたようにのびきった乱れ髪、朱色で鬼瓦のような恐ろしい顔相をしている。自らの境涯をあたりの深山幽谷になぞらえて物語り、雪月花を愛でる山廻りの様を現じてみせると、再びいずこともなく消えていってしまう。
恐ろしいイメージが先行しがちだが、能に登場する山姥は、けっして「鬼」、「悪いもの」といった単一的な存在では描かれない。山姥は自ら省察する。「そもそも、山姥は生まれた所も、住む所も、定かではありません。雲や水のように、どんな山奥でも行かない所はありません。だから人間ではない。雲のように変幻自在に、あるときは鬼女の姿として現れる」鬼女の輪郭を持ち、山々を飛び回り続ける、広漠として際限のない大自然そのものの象徴なのだ。一方、時には人々を救う身近な存在でもあった。「人間たちとの交わりはある時は山人の重き薪に肩を貸し月の出ともに里までも送って出ることもある。またある時は機織の女の部屋に入って、鶯のように糸を紡いで、手伝って人を助けることばかり。姿は人の目に見えず『目に見えない鬼』がやったことと言われて、この世は皮肉なもの」と自分の境涯を語り嘆息するシーンは物悲しい。(川西十人『能の友シリーズ 山姥』白竜社より)
大拙はこの山姥の姿に「愛の原理(the principle of love)」を見出した。大拙が残した『禅と能』は(※本書は絶版となっているため要約されたレジュメより引用)には「山姥といふのは、文字通りには『山の老女』といふのだか、それは吾々誰の心にもひそかに動く愛の原理を現してゐる(represents the principle of love secretly moving in every one of us)」と記されている。ここでも若々しく、瑞々しいイメージではないのだ。このようなイメージは表面的結果に過ぎない、普通自分たちは意識せずに、終始誤用していると大胆に宣言している。
「愛そのものはよく働く農婦のやうに、やつれた姿をしてゐる。他のものの爲に苦労を重ねるところから、その顔は皺だらけで、その髮は眞白だ。解決しなければならぬ難問を多く身に附けてゐる」
『山姥』の語り部は、愛のこの観念を作品の中に盛り込み、山姥を、自然と人間の背後にある眼に見えない力としたのではないか、大拙はそう考えた。このような愛は、荒々しい息遣いで舞い続け、もはや人間のあいだに留まることなく、やがて善悪を越えた大自然の力として飛翔し、最後には人々の手の届かない未知の世界まで飛び去っていく。
LOVEという言葉がキリスト教を背景とした西洋から入ってきた明治期、この言葉に最初に出合った日本人たちは、どう訳そうか頭を抱えたに違いない。結果、「詰まる息」、「荒い息」を通奏低音として含む語源を持つ漢字が目の前に残ることになった。今こうしている間も、自分の知らないあちこちで寄せては返す波のように人々の胸が愛にふくらんだり、しぼんだりしているかと思うと、少し空気が足りなくなってきそうだ。
文・『1/f(エフブンノイチ)』編集人
長尾契子 Keiko Nagao
------------------------------------------------------------
こちらは、最新号『1/f』vol.9「息をしている。」より、期間限定公開記事(07/09〜7/30まで)です。その他、「荒い息」にまつわる映画作品を紹介しています。最新号『1/f』vol.9にて、ご覧いただけます。7月のオンラインショップ・オープンは【7/10(土)〜7/16(金)】です。最新号の詳細はこちらのバナーから。